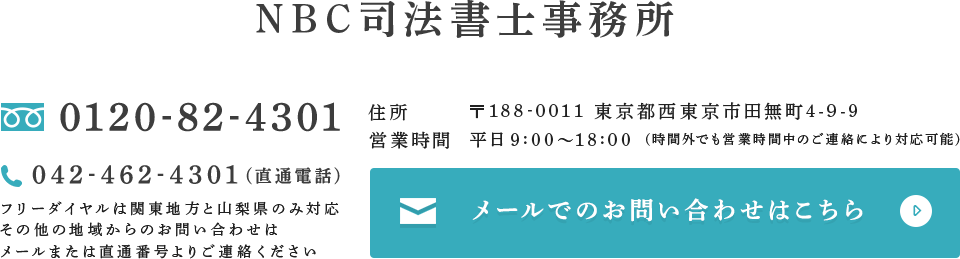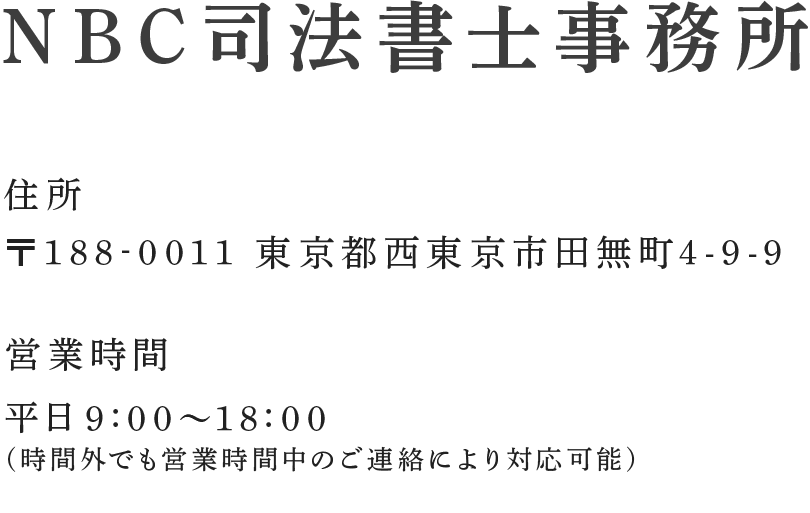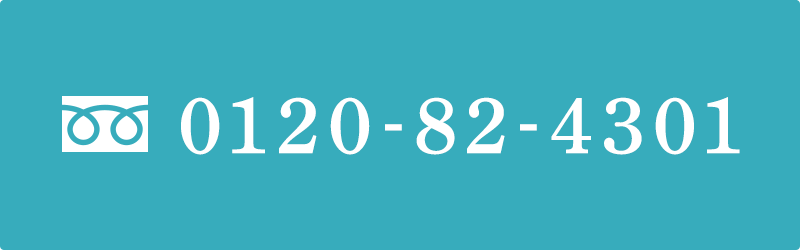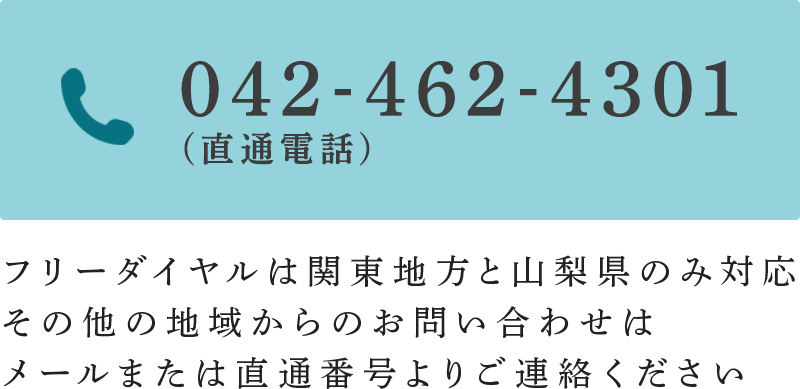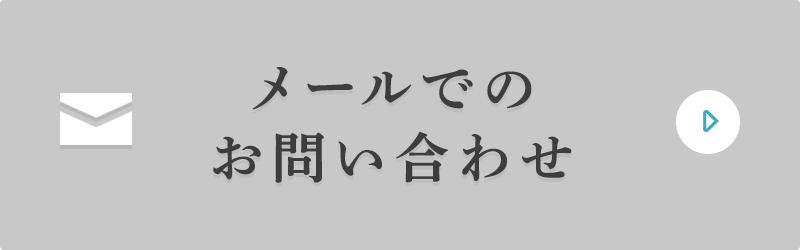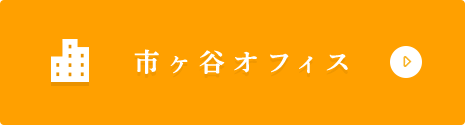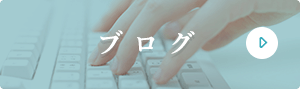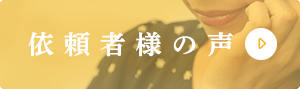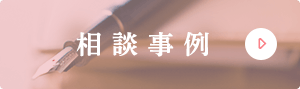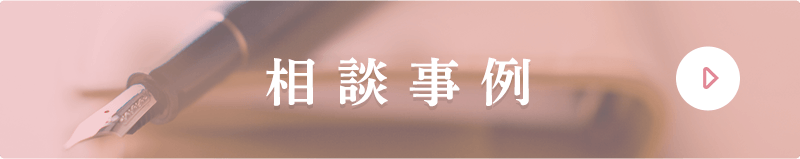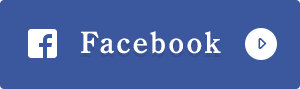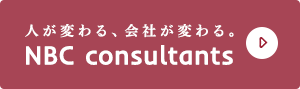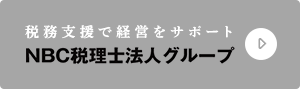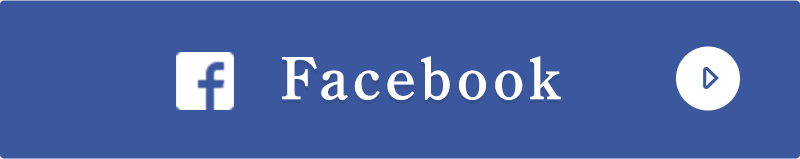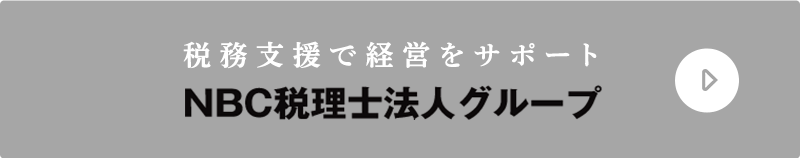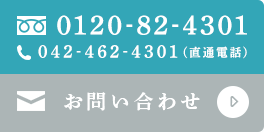本年10月より消費税が上がる事、それとともに消費が冷え込むことを抑えるため、国がキャッシュレス化を進め一定要件を満たすとポイントをつけるという政策を行う予定です。
それに合わせ当事務所も課題はあるものの、クレジットカードの利用をできるように進めております。現在、3月1日よりVISA、Master、アメックスカードが使用できるようになる予定です。なおご依頼いただいた内容によってはカードの支払いができない場合がありますので、ご了承願います。
2019.02.21更新
クレジットカード対応のお知らせ(予定)
投稿者:
2018.12.13更新
2018年から2019年の年末年始の営業時間について
早いもので12月も3分の1が経過してしまいました。
また1年間当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
当事務所の年末年始の営業のご案内をいたします。
12月28日(金)まで 通常営業(8時30分から18時00分まで)
12月29日(土)から1月3日(木) 休み
1月4日(金) 9時から16時頃まで ※
1月5日、6日 休み
1月7日(月)から 通常営業
※1月4日については、午後のお問い合わせの状況により早じまいをいたします。
来年も引き続き当事務所をご愛顧いただきますようお願いいたします。
投稿者:
2018.09.07更新
遺言・相続無料相談会のご案内
最近、相続や遺言についての相談がさらに増えているように思えます。
特に、相談者様ご自身や、ご両親等の家族に関して、今からできる準備はないかというご相談が増えています。
相続が発生した後からではなく、生前から意識されている方々が増えているようです。
当事務所でもそのようなお客様のご要望にお応えすべく日ごろから相談を承っております。
そして、日ごろお仕事で忙しい方にも相談できる場をご提供すべく、休日無料相談会を行っております。
今回は、9月29日10時~14時に開催致します。詳細は下記のとおりです。
是非お気軽にご参加ください。
遺言・相続無料相談会
開催日時 平成30年9月29日 土曜日 午前10時から午後2時まで
※最終受付時間 午後1時
相談時間 一組1時間
場 所 NBC司法書士事務所
電話番号 0120-82-4301
メール shiho.tyoshida@dream.com
投稿者:
2018.08.21更新
取締役が認知症になっってしまったら
お客様より、会社役員の変更登記の依頼がありました。
取締役を一人退任させたいとのこと。
取締役の娘さんから要望があったそうです。
娘さんからの要望?と疑問を抱きつつよくよく話をきいてみると・・。
取締役に就任している方は、認知症により成年後見制度を利用してるそうで、
娘さんはその後見人に就任しているとのこと。
成年後見が開始したため、裁判所から指導があったようです。
そして今回登記をすることになったそうです。
成年後見制度を利用するということは、本人の判断能力が著しく減退していますので、
取締役という会社に対して高度な責任を負う職責は荷が重すぎますよね。
この点、会社法上でも、成年被後見人は取締役になれないと定められています。
成年後見が開始しますと、今回の取締役の退任もしかり、他にも財産管理の面でいろいろ制限がかかりますので注意が必要です。
投稿者:
2018.08.03更新
今日は何の日?
突然ですが、問題です。
今日は8月3日です。
さて何の日でしょう。
・
・
・
・
コロンブスが初めて探検に出発した日
フランス7月革命が終わった日
パナマ運河が完成した日
などなど
世界的に有名な事象がたくさんありますが、いずれも不正解です。
答えは、
NBC司法書士事務所プレゼンツ、FM西東京ラジオ放映の日です!!!!!
先月より、毎月第1金曜日17時30分から生放送です

人生100年時代のリスクと相続をテーマに、豊富な知識、長年の経験に基づいた耳よりの情報をご提供します。
ぜひぜひ、ラジオを聴いてください。
もし、聞き逃してしまった方は、FM西東京のホームページで視聴できますので、そちらも宜しくお願いいたします!!
投稿者:
2018.07.12更新
たまにあります。
自宅を建て替えたお客様の保存登記、抵当権設定登記のため、 お客様宅へ書類を預かりにいきました。
事前に金融機関から担保にとる不動産は自宅と敷地と聞いていまし た。
部屋にあげてもらい、挨拶後、 準備して頂いた書類を確認していきました。
抵当権の設定登記には、 対象となる不動産の権利書が必要になります。
冊子になっている権利書を、今回の対象物件の権利書であるか、 土地、建物と確認していきました。
建物は、 建て替えなのでこの冊子にあるものは建て替え前の家の権利書です ね。
ところが、金融機関から対象物件は新しい自宅と敷地のみと聞いていたのに、 まだ他にも物件があるではないですか。
お客様に事情をうかがったところ、近隣住民で所有している私道? 空地?のようなものだそうです。
通常金融機関は、 融資にかかる物件をすべて担保にいれるのですが、 金融機関でも把握しきれないことがあるのですね。
後日、金融機関へ知らせたところ、 やはり把握できていなかったとのことで、 担保の対象となりました。
今回に限らず、私道等は普段の生活でも意識することはありませんし、相続登記などでも漏れたりすることが、
たまにありますので、注意が必要ですね。
投稿者:
2018.07.02更新
休日遺言・相続無料相談会開催のご案内
東京では6月にすでに梅雨明け宣言がありましたね。
夏本番がやってきて早速夏バテしそうです。。。
でも今週末から梅雨空復活の予報です。
個人的には毎年不思議に思います。梅雨明けたはずなのに梅雨より梅雨空
そんな今日この頃ですが、天気に負けず今月も無料相談会を開催します!
お盆に家族で相続についてお話しなさるご家庭もあるかと思います。
お盆前に、相続、遺言につてい専門家に相談をしてみませんか?
ご希望の方は次の日時で開催しますので、奮ってご参加ください!
遺言・相続無料相談会
開催日時 平成30年7月14日 午前10時から午後2時まで
※最終受付時間 午後1時
相談時間 一組1時間
場 所 NBC司法書士事務所
電話番号 0120-82-4301
メール shiho.tyoshida@dream.com
※無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
※無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
※事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。
投稿者:
2018.06.29更新
想定外。。。
先日、遺産整理業務を受任し、指輪や装飾品等をお預かりしました。
形見分けで、相続人で分けるのだろうかと思っていたところ、
依頼者の要望により、換価した場合いくらになるか調べるため質屋に待っていきました。
鑑定書等はないため財産的価値は乏しいだろうと考えていました。
数が大量にあったためしばらく待っていたら驚きの結果が。
予想に反し、いくつも値がつくではありませんか。
値段はまちまちですが、買取りの対象になるものが多数ありました。
質屋へ買取りをお願した経験がなかったため、個人的には意外な結果でした。
わからないことを自分の感覚で判断してしまうと、思わぬ結果を招くので要注意ですね。
投稿者:
2018.06.20更新
休日無料相談会開催
近頃、相続手続や遺言書の作成に関するお問い合わせを受けることが多くなりました。
そこで、休日無料相談会を開催致します!!
両親の相続手続きで大変な思いをしたので、次の世代には負担を軽くできるようにと、
遺言書を作成される方が増えています。
しかし、遺言書はただ書けば良いというものではありません。
法律に則り書かなければ、法的な効力は生じずせっかく書いたものが台無しになってしまいます。
作成にあたっての注意事項や、相続が争族にならないためのちょっとしたポイントをお教えします。
遺言書の作成を考えている方や、その他お困りのあるかたは、是非この機会を有効にご利用ください。
無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。
遺言・相続無料相談会
開催日時 平成30年6月23日 午前10時から午後2時まで
※最終受付時間 午後1時
相談時間 一組1時間
場 所 NBC司法書士事務所
電話番号 0120-82-4301
メール shiho.tyoshida@dream.com
投稿者:
2018.06.11更新
「本人の認知症等に伴う判断能力の低下にご注意」
先日、ご相談のあったお客様の話です。
そのお客様のお父様から、お客様への不動産の売買に伴う登記に関するご相談がありました。
登記手続に必要となる書類を一通り案内し、当事者のご本人様確認のためお父様とも面会する必要があることを説明しました。
するとお客様は「父は少し認知症ぎみですが、自分が事務所まで連れてくるので大丈夫です。」とのことでした。
贈与や売買等、人が法律に関する行為をするためには、本人にその行為を正常に判断する能力が備わっている必要があります。
認知症の程度にもよりますが、認知症の場合、自身の法律に関する行為を正常に判断するには困難を伴うことが往々にしてあります。
お客様へ、主治医からお父様の診断書をもらうよう案内したところ、案の定、法律行為不可の診断がおりました。
現在は、成年後見制度という、お父様本人の財産管理を裁判所が選任した代理人が行う制度を利用するための手続きを行っています。
このように、認知症になってしまいますと、不動産の売買や贈与、相続に伴う遺産分割協議、自社の株主としての議決権行使などなど、
法律行為は大きく制限されてしまい、当初の計画がすべて頓挫してしまいます。
また、場合によっては成年後見制度の利用を検討するなど、対応が必要となりますので、ご注意が必要です。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (1)
- 2024年07月 (1)
- 2024年06月 (1)
- 2023年12月 (2)
- 2023年05月 (2)
- 2023年04月 (1)
- 2023年03月 (3)
- 2023年01月 (4)
- 2022年11月 (1)
- 2022年07月 (1)
- 2022年06月 (1)
- 2022年03月 (3)
- 2022年02月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年01月 (2)
- 2020年07月 (2)
- 2020年04月 (3)
- 2020年03月 (1)
- 2020年02月 (3)
- 2019年12月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年07月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (1)
- 2019年02月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年09月 (1)
- 2018年08月 (2)
- 2018年07月 (2)
- 2018年06月 (4)
- 2018年05月 (1)
- 2018年04月 (1)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (1)
- 2017年09月 (1)
- 2017年06月 (1)
- 2017年03月 (1)
- 2017年01月 (1)
- 2016年09月 (1)
- 2016年06月 (2)
- 2016年04月 (1)
- 2016年01月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年04月 (1)
- 2015年03月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年05月 (1)
- 2014年02月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年04月 (1)
- 2013年02月 (1)
- 2012年07月 (1)
- 2012年04月 (1)
- 2011年11月 (1)