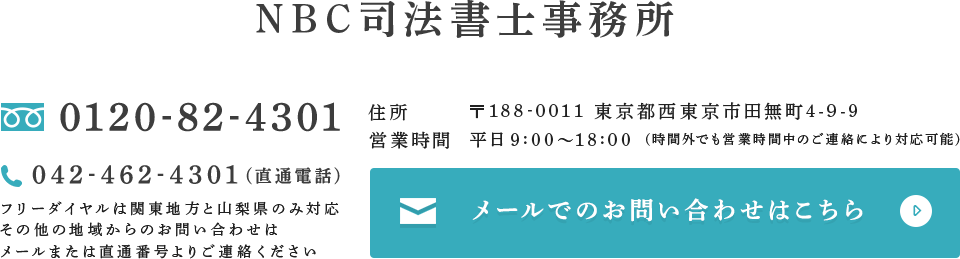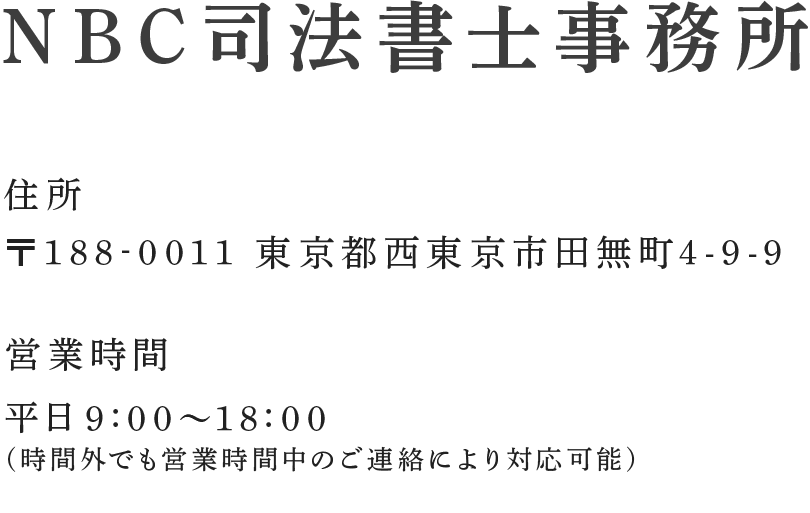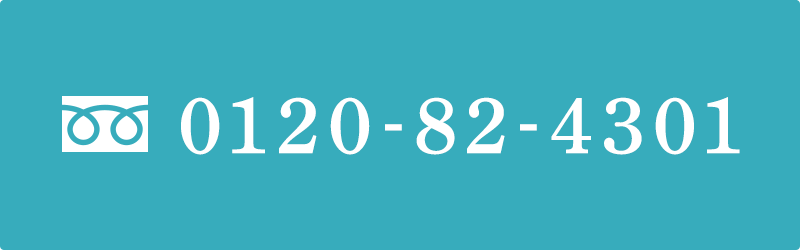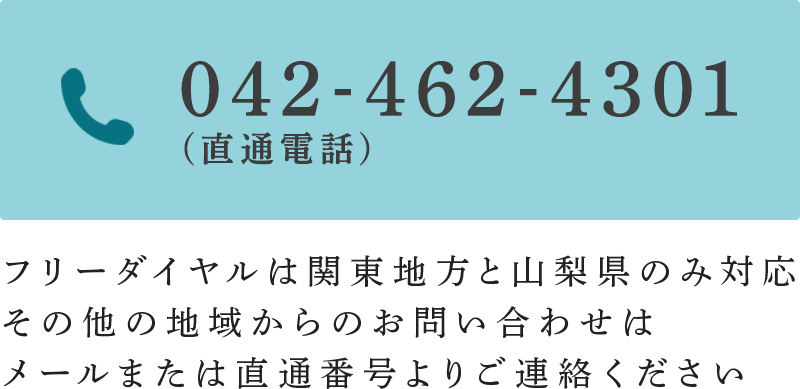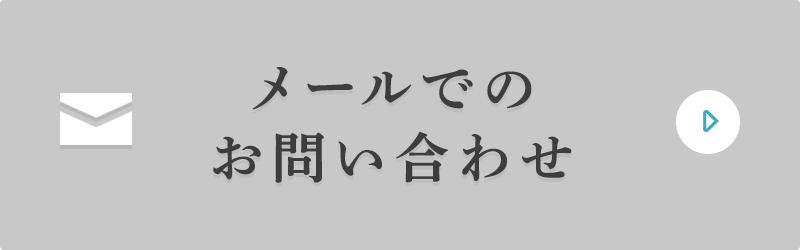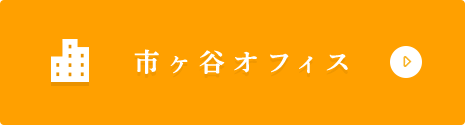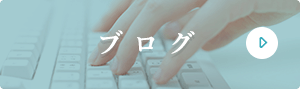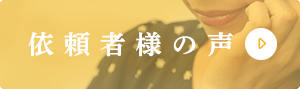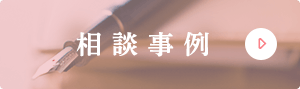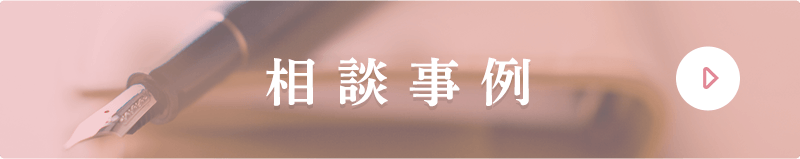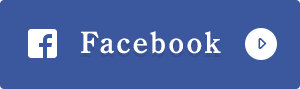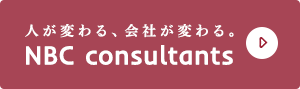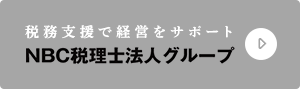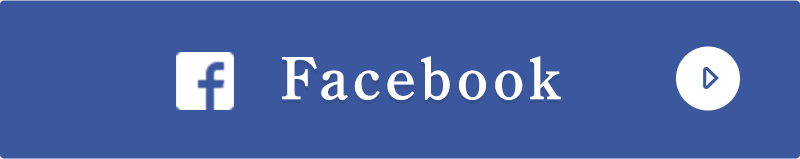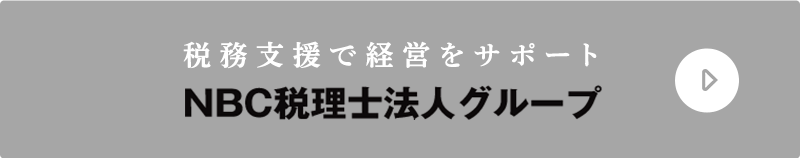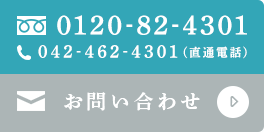司法書士の仕事ってどんなことするの?
主に登記でしょ!
確かに正しいですがそれだけではありません。
1.生前の認知症対策としての、任意後見契約や民事信託、不運にも認知症になってしまえば成年後見の申立。昭和時代には、万一認知症になったらなどという事は考えなかったと思います。しかし今は、万一認知症になった時、自宅を売却して施設に入ろうとしても「成年後見人を選ばないとダメ」、認知症の方の定期預金を降ろして、施設に入ろうとしても、銀行は原則として認知症とわかったら、成年後見人が選ばれるまで「預金を凍結」という時代になっています。
なってしまうかどうかわかりませんが、今や認知症対策も考える必要があるのではないでしょうか?
2.死後の財産の引継ぎ
死んだあと子供たちが、相続財産で揉めてしまうのは悲しい事ですよね。完ぺきとは言わないまでも、遺言である程度紛争を防止できます。また例えば夫婦二人で子供がいない場合、夫が100%の割合で自宅を持っていたとして死亡後妻に100%自宅を相続させたとしたら奥さんが亡くなった後奥さんの兄弟や甥姪に財産が通常行きます。「それは嫌だ」という場合民事信託を使う方法もあります。
今や司法書士はこんなこともするのです。
しかし葬儀の手配、施設の紹介、身元保証などは司法書士単独では行えないので、一般社団法人めいぷる小平の協力が必要になります。
今回の主な相談項目は、遺言・相続・成年後見・民事(家族)信託などについての無料相談になりますが、分からないので取り敢えずという方も可能です。
日時 令和5年6月10日(土)午前10時から午後4時(午後12時から1時は休憩)
場所 NBC司法書士事務所(西東京市田無町四丁目9番9号)
連絡先 TEL 042-462-4302 E-mail shiho.tyoshida@dream.com 担当 吉田
予約締め切り日 令和5年6月8日(木)午後5時
1組 1時間の完全予約制。(最大4組) 予約枠が空の時は、事務所を閉める事がありますので、飛び込みはご遠慮願います。
なおこちらからしつこいセールスは行いません。