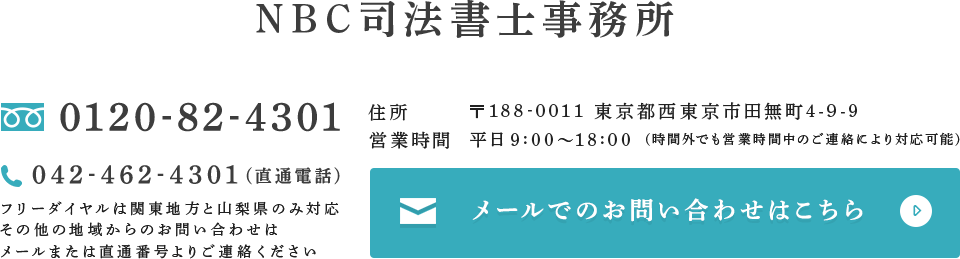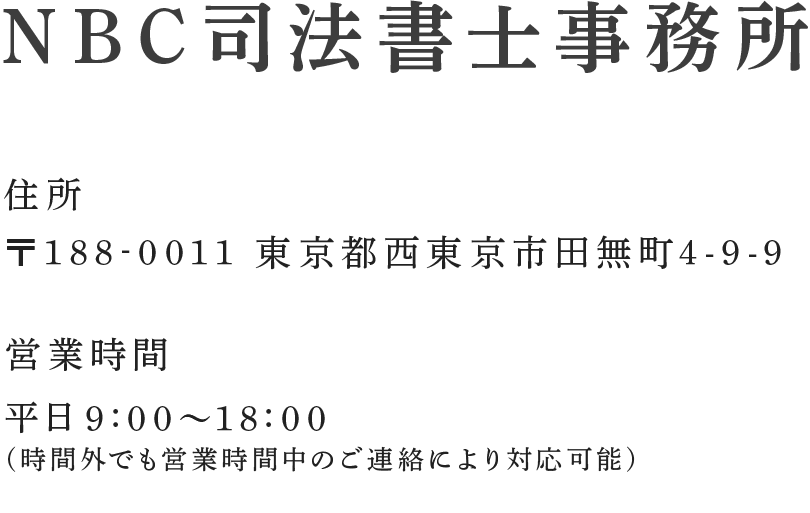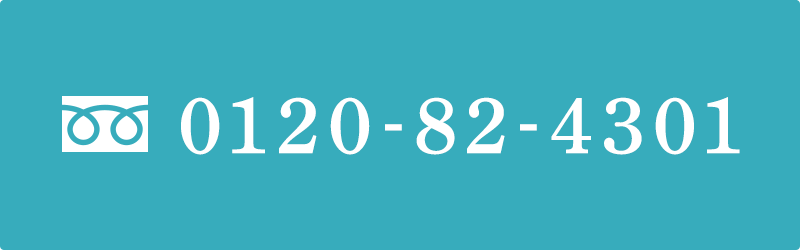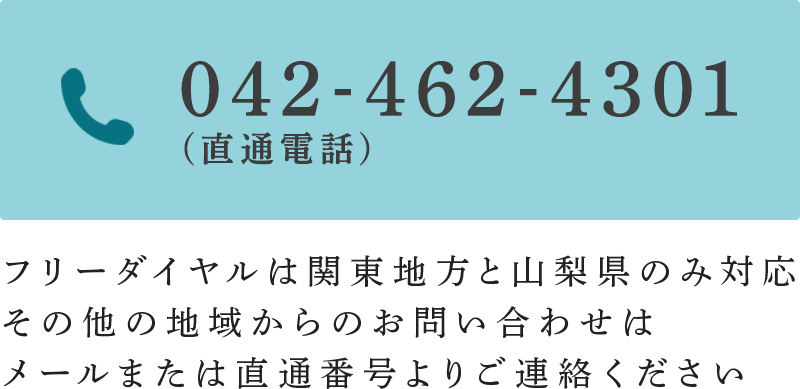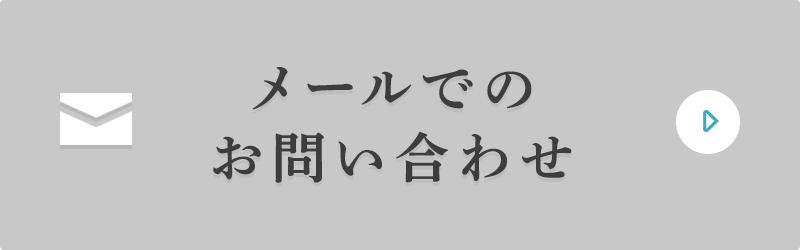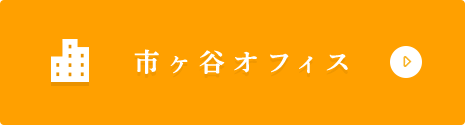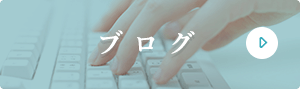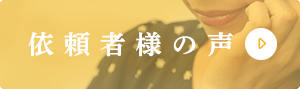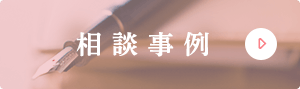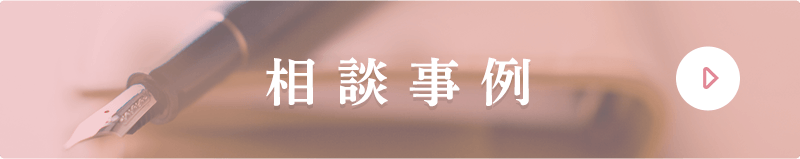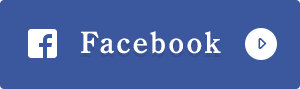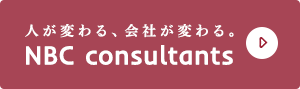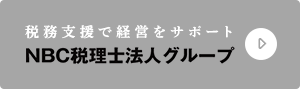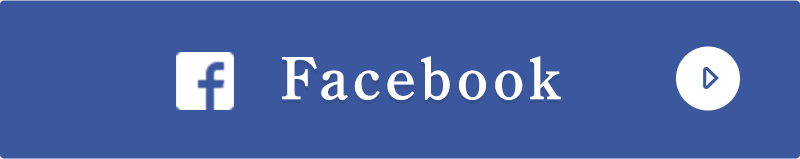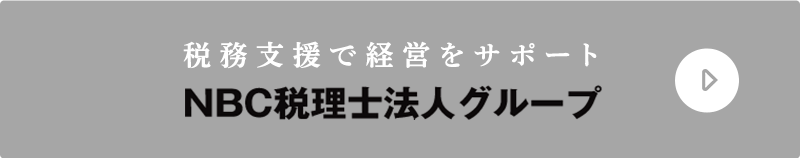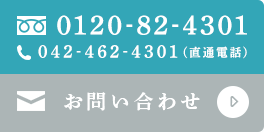1. 生命保険金の性質
生命保険金は「受取人固有の権利」とされ、原則として 遺産分割の対象になりません。
したがって、受取人を指定しておけば、遺産分割協議を経ずに現金を渡せます。
2. 遺留分に対する扱い
裁判例(最判平成16年10月29日など)では、
「著しく高額な保険金」は特別受益に準じて、遺留分侵害額請求の対象に含まれる場合があります。
つまり「生命保険金=完全に遺留分対策になる」とは言い切れず、金額の妥当性 がポイントです。
3. 典型的な活用法
(1) 特定の相続人に現金を残す
事業を継ぐ子や、介護を担った子に多めに渡す。
他の相続人には遺産から分配。
保険金が常識的な範囲なら、遺留分侵害請求の対象外になり得ます。
(2) 不動産の偏在を補う
自宅や事業用不動産を1人が相続すると、他の相続人が「不公平」と感じやすい。
そこで、他の相続人に保険金を渡して公平感を持たせる。
(3) 遺留分請求への備え
万一、他の相続人が遺留分侵害額請求をしてきた場合に備え、現金(保険金)を確保しておく。
不動産しかないと現金化が難しいため、生命保険で流動資金を用意する意味がある。
4. 注意点
保険金が相続財産の大半を占めるような設計は、特別受益とみなされやすい。
保険契約の「誰が契約者か、誰が保険料を払ったか」によって、相続税・贈与税の扱いが変わる。
生命保険金は相続税の課税対象に含まれるため、節税と遺留分対策を同時に満たすには慎重な設計が必要。
✅ まとめ
生命保険は「遺留分を侵害しない範囲で特定の相続人に現金を残す」手段として有効。
ただし 高額だと特別受益扱い になり、遺留分侵害額請求のリスクがある。
個別具体的な相談は、NBCコンサルタンツで行っています。